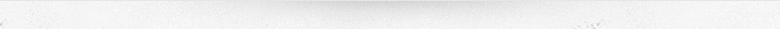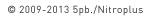試し読み 第1回
STEINS;GATE 永劫回帰のパンドラ 第4章「虚像」
Die Definition von Wahnsinn ist,
immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
(狂気とは、何度も同じことを繰り返しながら、違う結果を期待することである)
――Albert Einstein
「ぐすっ……ぐすっ」
その子はずうっと泣いていた。
大小の機械に取り囲まれた鉄臭い空気の中、シートにうずくまって、ずっとずっと。
これだけ泣けば、涙などはすっかり枯れ果て、その愛らしい眼からは一滴の水分も流れないのではないかと思われたが……しかし彼女は泣き続け、絶え間のない幾筋ものしずくが頬を伝っては落ちていくのだ。
「ちょっと、かがり」
タイムマシンのドアが外から開き、栗色の髪をした少女が声をかけてきた。少し苛ついた口調だ。
「いつまで泣いてるつもり?」
「…………」
「しっかりしなきゃ駄目だ。まゆねえさんの気持ちを考えろ」
「……ママ?」
そして再びベソベソと泣き出そうとするその口に、栗毛の少女——橋田鈴羽は、人差し指を当てた。
「だから、泣くんじゃない。鬱陶しい」
「でも……」
「いい? ここまで来た以上、かがりも〝ワルキューレ〞の一員とみなす。あたしの部下として扱う。非戦闘員じゃないからな」
「…………」
「ここは1975年だ。知ってる人間は誰もいない。父さんもまゆねえさんも出生してない。つまり、誰も守ってくれないんだ」
「う……」
「自分の身を守るのは自分だけだと思うこと。いい?」
「うん……」
気丈なかがりは、ようやく、泣いている場合ではないことを自覚したようだった。
自分にはやるべきことがある——そう思いついて、涙をぐっとこらえようとする。
その試みは、あまり上手くはいっていなかったが、うずくまったまま時を浪費しているよりはずっといい。
そう考えられるのが、この女の子、椎名かがりの賢さなのだ。
「了解したら、これに着替えて」
近くの店で手に入れてきたのだろう。鈴羽は、70年代の女の子がよく着ていたチェックのジャンパースカートと白の襟付きブラウスをかがりのヒザの上に置いた。
そして自分も、この時代のジーンズとシャツに着替え始める。
「着替え終わったら街へ出るよ。あんたにも手伝ってもらうからね」
「うん」
「あんまり時間がない。この時代の人間にタイムマシンが見つかったら大騒ぎだ」
マシンが到着したラジオ会館の屋上は、あまり人が来るような場所ではないが——この時代には、マシン隠蔽に協力してくれるはずの秋葉留未穂はまだ生まれてきていない。用心に越したことはないだろう。
「何か失敗したら、またマシンで時間を戻ればいいんじゃないの……?」
着替えながらおずおずと訊いてくるかがりに向かって、鈴羽は首を振った。
「燃料の問題があるんだ。ジャンプできる回数は無限じゃない。肝心の場面で動作しなかったら、話にならないからね」
「そうなんだ……」
「ほら、行くよ」
70年代ファッションに身を包んだ鈴羽は、同じくこの時代に同化したかがりを促して、マシンの外へ出た。
「っ……?」
まずかがりを襲ったのは、目が慣れるまでにしばらくかかりそうなほど強い陽光だった。
青空と呼ぶには、あまりにも汚らしくすすけてしまっているこの時代の東京の空——。林立する工場の煙突から噴出している得体の知れない煙や粉塵、そして、群れをなして地を這う自動車の真っ黒な排ガスなどが光化学スモッグを生み、都市の上空を死のベールのように覆ってしまっている。
しかし、それでもかがりにとっては初めて経験する〝澄んだ空〞だったのだ。太陽の光がこんなにまばゆいものだと、彼女はビデオや本の中でしか知らなかった。
「あたしが子供の頃は、まだこんな感じの空だった。少しだけど覚えてるよ」
鈴羽も、まぶしさに目を細めていた。
彼女たちが生きていた時代、すなわち第三次世界大戦後の東京の空は、核兵器がもたらした気象変動によって常ににび色の雲に占拠されていた。太陽はその向こうからボンヤリと淡い光を投げかけてくるだけで、これほどに激しい陽射しを浴びることなど皆無だったのである。
「空気が、美味しい……」
かがりの感想を聞いたこの時代の人々は、一様に首をかしげてしまうだろう。
だが、時にフィルター付きのマスクが必要だった2030年代に比べれば、ここははるかに清浄なのだ。
「分かるだろう、かがり? 父さんたちがどうして世界線の改変に全てを賭けていたのか」
「…………」
「世界線がどうとか歴史がどうとか、そんな理屈はあとでいい……今はただ、この空の色を守りたいと思えば」
それは、かがりに——というよりも、自分自身に言い聞かせているようにも聞こえた。
「よし、ミッションを開始する」
タイムマシンのドアを閉じる。
自動的にロックがかかり、これで、鈴羽の生体認証がなければ乗り込むことすら出来なくなる。万が一、マシンが誰かに見つかったとしても、これがいったいなんなのかすぐに知られることはな
いだろう。
「これを見て」
少女の背中をポンとひとつ叩くと、ポケットの中からプリントされた写真を取り出す。
「それは?」
「『IBN5100』というレトロPC。あたしたちの時代に存在していたものは、どれも満足に動かない。けど、この時代なら完動品が入手できる。これを手分けして探す」
「うん」
「連絡はこれで。といっても、通信できる距離はかなり短いらしいから、気休め程度だと思って」
かがりに小型のトランシーバーを渡す。階下の店で入手したものだ。
「えっと……オーキードーキー」
「九十分ごとに、このビルの前に集合。状況を確認。それを繰り返す。いい?」
「オーキードーキー」
「よし、行こう」
屋上からラジオ会館内へ続く鉄扉へ向かう。
「鈴羽おねーちゃん……」
「んん?」
「……ママは……」
「うん」
「痛い思いとか、したのかな」
「…………」
「苦しい思いとか……したのかな」
鈴羽の脳裏に、最後に見た父やまゆりの姿が一瞬だけ浮かんで……そして消えた。
「分からない。あたしたちがタイムマシンを使って歴史を改変したら……結果、あの時間はなくなってしまうはずだから……」
「そっか……」
かがりは、鉄扉をくぐる前に、もう一度空を見上げる。
巨大な積乱雲が、天を突くようにどこまでも高く昇っていきつつあった。
——これってなぁに? バクダンのくも?
もっとずっと小さかった頃、写真を見ながら母に質問したことを思い出した。
——ううん。これはね、入道雲って言うんだよ。夏になるとね、モクモク〜って空に出てくるの。
——なんか、上にのれそう!
——う〜ん、ちょっと無理かなぁ。雲の上には〝天国〞があるから、神様に断られちゃうかも。生きてる人はダメですよ〜って。
——えー、そっかぁ……。
——だから、かがりちゃんはずっとママのそばにいてね? 雲の上なんか行かないで。
——うんっ。ママもね。
——もちろんだよ。ママはどこにも行きません。
そして母は——椎名まゆりは、愛しい娘の髪を優しく撫でてくれたのだ。
「…………」
あの時の笑顔を思い出してしまったかがりは、再びこぼれ落ちそうになった涙をぐっとぬぐった。
ポケットの中から、色あせた緑の〝うーぱ〞キーホルダーを取り出し、じっと見つめる。まゆりが最期に持たせてくれたものだ。
「ママ……嘘つき……」
その哀しいつぶやきは、しかし、先に立ってラジオ会館の中へ足を踏み入れていた鈴羽には聞こえることはなかった。
つづく